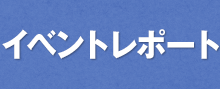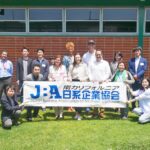2015/4/24
「グローバル時代のリーダー開発 ~エグゼクティブ・コーチングと組織開発~」報告
去る4月24日、トーランスのToyota USA Automobile Museumで、第182回JBAセミナーを開催した。組織を変革しビジネスを牽引するリーダーの役割が重要となる現在において、コーチングを通していかに経営幹部や現地のキー人材をリーダー開発するかを、コーチ・エィのお二人が講演。具体的なリーダーおよび組織開発についての取り組み事例も含め、分かりやすく解説した。
第1部
 |
[講師] 伊藤 守 さん 株式会社コーチ・エィ創業者、代表取締役。国際コーチ連盟(ICF)より日本人として初のマスター認定。2001年にエグゼクティブ・コーチング・ファームとして同社を設立。以来約26カ国、1700社以上のリーダー開発や組織風土改革に携わった。 |
コーチングの意味とその目的
コーチングの語源は馬車を意味する「Coach」。目的地までより早く運んでいくという隠喩である。現在、グローバル企業の多くがエグゼクティブ・コーチングを導入しており、アメリカではもはや常識となっている。
エグゼクティブ・コーチングの導入目的は、リーダーを洗練させること。リーダーは企業利益の29.2% を左右するとも言われるほどその影響力は大きく、リーダーの意識改革が会社変革の近道となる。伊藤さんは、伸びる企業ほど、重要度が高いながらも緊急度は低いと思われがちなリーダー開発や組織変革に投資をする傾向があると、コーチングの重要性を力説した。
リーダーシップに必要なことは、伝達力、外交力、革新性、部下の鼓舞力、専門性、短期的な成果、フィードバック、他者への協力などさまざまだが、その重要度は国によって全く異なるという。従って、時、場所、状況に応じて、リーダーに求められていることを的確に判断しないと、リーダーシップが発揮できないことになる。
コーチングの最終目的は業績を上げることだが、それには組織の成長基盤と、それを支える個人の成長基盤の2つの基盤が必要となる。個人の成長基盤には、コミュニケーション、リーダーシップ、プレゼンス、パーソナルファウンデーション、健康などの要素が必要となる。中でもプレゼンスは、顔が怖い、愛想がない等の特徴を持つリーダーには部下が恐れて近寄らなくなるため、重要な情報が上がりづらくなる。経営者に肝心な情報が入らないと企業の成長の鈍化につながるため、笑い話では済まされない。
伊藤さんによると、コーチングとは、制度や仕組み、ルールを作るのではなく、それを実行するキーパーソンを開発すること。コーチングは原則的に1 対1 で行われ、目標達成に向けて集中的、継続的、長期的に進められる。そのプロセスは最低8 カ月以上、経営者の中には4~ 5 年にわたりコーチをつける人もいるという。今求められるリーダーとは、「枠」に収まらず、創造的、革新的であることを求められる存在だからこそ、研修による指導法ではなく、コーチングによる開発が有効なのである。
コーチングは双方向の関係性を重視
コーチングは、組織風土の改革/醸成、役員のリーダーシップ開発、ロールマッチなどを目的に導入され、現場から提案できる風土、人を育てる風土、成長し続ける自律的企業文化の醸成など、企業風土の育成を目標としている。興味深いのが、カリスマ系のリーダーは自分のフォロワーを作ることに関心を持つが、リーダーの本来あるべき姿は組織内にさらに多くのリーダーを作ることに注力するということである。
コーチングでは、コーチが一方的に教えたりアドバイスを与えたりするのではなく、その人が何をしたいのか、どこに向かいたいのかなどを慎重に聞き取った上でコーチングを進める。人からの一方的な話だけでは主体性のない人材が育ってしまうからである。また双方向のコミュニケーションを取りながら本人の考え方や個性、組織の目的に合わせてプロジェクトをカスタマイズする。リーダーは、視点(View)の確保、つまり会社全体を見渡し、会社の現在・未来をはじめ、社員間で起こっていること、社員が遭遇していることやその対処法などを把握しなければならない。リーダーとしてのビューを手に入れるには、部下との間の信頼・協力関係がキーとなる。つまり、部下との関係構築の戦略がないとリーダーとしての役割は発揮できない。ま、チームとチーム、部署と部署など横のつながりも重要だが、これに関してはいくら連携を取っていてもEメールだけでは効果が十分期待できるのかは疑問だと、伊藤さんは語った。
第2部
 |
[講師] 栗本 渉 (わたる) さん 株式会社コーチ・エィ取締役。企業変革を推進するプロジェクトの企画から実施まで総合的に担当。海外では現地法人の次世代幹部輩出、現地人材活用に向けた組織変革プロジェクト等に携わり、シニアマネジメント層100人超にコーチングを実施。 |
考え方を変えるコーチングのプロセス
次に栗本さんが、「駐在員および米国人経営幹部の登用と育成の実例」をテーマに、現地化へチャレンジし、業績を上げ続ける組織を目指す日本人CEO、Aさんのコーチング例を紹介した。赴任期間が数年で終了するAさんが、残された期間でアメリカの組織の事業統括を実現し、後進の輩出に挑戦するというものである。
Aさんは非常に有能で、これまでどの海外支店でも業績を上げてきた。これに対して、後継者候補の米国人CFO、Bさんは会計士出身。営業部のトップに立てるかどうかは未知数。運悪くBさんは当時の営業トップとは不仲で、本社との関係も良くない。Aさんの願いは、業績を守りながらBさんをトップにし、自分が去った後も業績を上げる会社にするというものだった。
Aさんには日本人コーチが、Bさんにはアメリカ人コーチが付いた。コーチングのテーマは3 つ。①Bさんが後継にふさわしい人物となること(部下、本社、顧客の信頼を得ること)、②AさんがBさんや組織に変化を迫り、変化を引き出す力を持つこと、③Bさんの指揮の下、これまでを上回る業績が達成されること。
プロジェクトは、導入・開始→現状の棚卸し→目標設定→セッションの継続→中間確認→終了・評価のプロセスで進んだ。さらに成果を生むために、①フィードバックと現実認識(各種リサーチ)、②質問に基づく対話(コーチングセッション)、③新たな現場行動(アサイメントとアクション)の3つの方法を採用。①から③に進むことで情報と対話を組み合わせ、そこから創出した発想と行動を変化に結び付ける構造となっている。
①フィードバックと現状認識
(A)インベントリー: リーダーシップと組織状態の棚卸しとして、インベントリーを実施。リーダーとしての強みや弱みを把握する。
(B)ステークホルダー・インタビュー: Aさんの周りのキーパーソンたちにインタビューを実施。インベントリーでは分からなかった細かい現場の声をヒアリングする。
(C)成果検証のためのアセスメント: Aさんとコーチが協働して設問設計し、Aさんの目指す状態を具体化、明確化する。
②質問に基づく対話
①で得た情報をAさんとコーチで吟味。その際コーチからはいくつか質問し、Aさんは自由に思いをめぐらせて返答。コーチはAさんの着目点、着目理由、目標設定などを同じ目線で一緒に考えるが、基本的に
Aさんの話を聞くだけ。そうすることで、Aさんには自分はどう考えるべきかについての気付きが生まれる。
③新たな行動
対話による気付きがあっても、実行がなければ意味がない。そもそもコーチングの焦点は「行動すること」である。チームメンバーに働きかけ、今後の自己プランを発表するなど、実行を続けることで習慣が変わり、そこから新たな現場行動へと移る。とは言え、頭で分かっていてもなかなか実践できないもの。栗本さんは、その理解と行動の間を隔てる深い溝に橋をかけるのがコーチングであるとした。
こうした一連のプロセスを経て現れるコーチングの効果として、ビジョンの明確化、フィードバックの受容、自己認識の向上、新しい方法への挑戦、組織目標の明確化、より早い目標の達成、自身のパフォーマンス向上、反応ではなくより客観的な対応などが挙げられた。
Aさんの場合も、他人からフィードバックが来た時に客観的に冷静に受け入れられるようになり、自分の現在の立ち位置を認識できるようになったこと、感情的に反応するのではなく自分の行動を選択できるようになり、最終的には目標であったアメリカ人CFOのB さんがトップに昇格し、その後、ビジネスの業績も上がったことが紹介された。
参加者の声
Roger Cleveland Golf の矢田さん「マネージャーのポジションにいますが、部下を持った経験がなく勉強のために参加しました。セミナーを聞いて具体的なイメージがわきました」 Pasona NA, Inc.の柴原さん「管理職に就いたばかりで、もっと知識を付けるために参加しました。今日のお話を今後にどんどん生かしていきます」 |